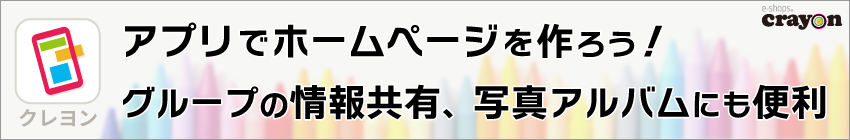
2018年度卒業制作の『ぶんじ白書』をWEB公開することができました。誤字脱字や誤った表現等ありましたら連絡をお願いいたします。全掲は夏までを目指しています。
東京初の民間人校長として杉並区立和田中学校で学校長を務めたリクルート(現・株式会社リクルートホールディングス)の藤原和博さんの『リクルートという奇跡』(文春文庫)のプロローグを少し長いが引用させていただこう。場面は、2001年の株主総会で当時代表取締役社長であった河野栄子さんに藤原さんが退任要求をする一幕である。
リクルートは情報産業の先端を走る会社のはずです。それが、、この株主総会のテイタラクはなんですか?
この4年、河野さんが社長になられてからずっと株主総会に出ていますが、20世紀中は確かにしょうがなかった面もあります。10年間で1兆円あまりの借金を返したわけですから、切り詰められるところは徹底的に切り詰めるで正解だった。
でも、もう21世紀なんです。ここからは、もう一度新しいリクルートを創業していく“リクルートマンシップが必要なんじゃないでしょうか。”リクルートマンシップ“というのは、新しいチャレンジによって道の市場を切り開いていく勇気と行動のことです。
あなたのプレゼンには、なんら未来へのビジョンがない。”リクルートマンシップ“という『見えない資産』を食いつぶして利益を上げているだけのように見えます。かつてダイエーの中内さんも、東京電力さんも、プレミアム付きの価格でリクルートの株を買ってくださったのは、そういうリクルートのエネルギーを、見えない資産を、評価したからではないんでしょうか。それが今や、守り一辺倒になっている。
河野さんは21世紀のリクルートのリーダーには、失礼ながらふさわしくありません。いつ、社長をバトンタッチするおつもりでしょうか。
もし、見事株式の上場を果たしてからというつもりならそれは間違いです。上場したら、いきなり大変な責任が新社長にかかってきます。それなら、いま、若手のなかから後継者を指名して、ここにいるみんなで上場に向けて社長として育てていけばいい。あなたが、この人はこうだからダメだとか、ここが足りないとか悪口を言っている場合じゃないんです。
どうか、一刻も早くも若手の後継者を指名して、見えない資産を食いつぶさないうちに、リクルートのエネルギーをもう一度復興する努力をしてください。
今日すぐにこの場で答えろと言っても無理でしょうから、役員会を開いていただいて、河野さんなりのお答えをお聞きしたい。
どうか、”リクルートマンシップ“に誓ってお願いします。
思わず、「これだ!」と唸ってしまった。国分寺高校には“リクルートマンシップ”“ならぬ、”ブンジ・スピリット“がある。しかし、まだそれは言語化されていない。だが、確実に50年にわたり作り上げ、そして連綿とつながれてきた何かがある。それらは国分寺高校が国分寺高校たる所以であり受け継ぎさらに大きくして世に広めなくてはいけないものでもある。
それと同時に国分寺高校の生徒の見えない資産を悪習や雰囲気、システムが食いつぶしているように感じるのもまた事実である。生徒自身が持つ才能や潜在能力が100%余すことなく発揮できる環境の改善の余地はまだまだある。都立だから授業料が安いと思ってはいけない。一番の授業料はこの最も多感で活発な時期という時間であることを見つめ直す必要があるだろう。
そこで、我々は本書に3つのテーマを設定し、統計、分析を行い、そのうえでこれからの学校生活改善のための提言を行うことにした。テーマは以下の3つである。
1.前時代的、非合理的な学校生活における悪習の打破
2.学習、部活、行事などの学校生活におけるノウハウの蓄積
3.“BUNJIブランド”の確立
ひとつ目は生徒の時間を大事にすべきだという思いからだ。国分寺生は「忙しい。」と急き立てられて日々を過ごすうちに、本当に忙しいと感じてしまい生活にゆとりを失ってしまっている。膨大な量の課題や無意味な伝統などが生産性に見合っているかどうかを検討した。
ふたつ目は自分たちで生み出してしまうムダな時間を減らすためだ。学習ノウハウが蓄積されれば予備校に通う必要性もなくなり金銭的にも時間的にも余裕が生まれる。行事もインプルーブメントが行われれば、国立高校に対抗できる都内屈指の高校文化祭になるポテンシャルを確信しているからである。
最後は進学実績や文化祭などでも国立高校には勝てないという思いからである。そこで必死に努力しようなんて思ってはいけない。最終的に社会に出た時に、奇抜なアイデアを出し、的確な人材起用に、理解しやすく業務計画を立てる人間になればよい。所詮、大学受験など上意下達の事務処理能力を図る試験に過ぎない。実務段階で働くのは国高の卒業生、それを顎で使うのは国分寺生という風になるべきなのだ。
今回われわれはアンケートを行い、センター得点率を基準として様々な相関を測定した。科目数等にばらつきがあるため、明確な指標とは言えないが、ある程度傾向が見られたものに対して分析を行った。とはいっても、科学的なレポートではなく、ももんが倶楽部の意見を交えた読み物と思ってもらって構わない。これから書いてあることははっきり言ってめちゃくちゃである。だから何だというのだ。言いたい放題やる。やりたい放題やる。それが来年も、同様の作品が作られることを期待する次第である。
<授業は神か>
授業は神か。読者の皆様にはよくわからない喩えになってしまったが、養老孟司さんの『バカの壁』(新潮
新書)の「NHKは神か」という一節を基にした喩えだからである。少し引用させていただこう。(<>は筆
者注)
<NHKは神か>
私自身は、「客観的事実が存在する」というのはやはり信仰の領域だと思っています。なぜなら、突き詰
めていけば、そんなことは誰にも確かめられないのですから。今の日本で一番怖いのは、それが信仰だと知
らぬままに、そんなものが存在する、と信じている人が非常に多いことなのです。
ちなみに、その代表がNHKである、というのが私の持論です。NHKの報道は「公平・客観・中立」が
モットーである、と堂々と唱えています。
「ありえない。どうしてそんなことが言えるんだ。お前は神様か」と言いたくなってしまう。まあ神様と
までは言わなくても、「あなたはイスラム教徒化キリスト教徒化ユダヤ教徒なのか。そうじゃないのならば
、どうしてそんな”正しさ“を簡単に平気で主張できるのか」と聞きたくなってしまいます。
国分寺高校の教員は耳にタコができるまで「授業を大切にしろ」と繰り返す。だから、私は「授業は神か」といつもボヤかずにはいられない。教員は、授業をすることで給料をもらっているわけだから、授業不要論があがろうものなら、教員の家族は路頭に迷ってしまう。橋下徹が主張する、公立学校民営化などはもってのほかであろう。(これには私も反対である。どうでもいいことだが。)だが、授業を受ければ学力が上がるのだろうか。
授業について [授業は楽しかったか]
センター得点率 の AVERAGE
あまりそう思わない
74.77272727
そう思う
77.72727273
とてもそう思う
80.625
全くそう思わない
76
回答者平均
76.78861789
これはアンケートでこれはアンケートで授業を楽しかったと答えた人のセンター平均得点率は平均を3ポイントも上回った。恐ろしいことである。授業を楽しいと感じない人はどちらも平均を下回っており、授業を楽しいと感じれないだけで大学入試が不利になるのだ。教員生徒双方に授業を楽しむ工夫が必要であることは間違いない。
授業について [授業はわかりやすかったか]
センター得点率 の AVERAGE
あまりそう思わない
74.35897436
そう思う
77.6
とてもそう思う
82.5
全くそう思わない
76.66666667
総計
76.78861789
授業のわかりやすさも同様である。授業をわかりやすいと感じる理解力の高い生徒は平均を6ポイント近く上回った。逆に、理解力の低い生徒はどちらも平均を下回っている。このことから私たちは、もとからできる生徒(授業を楽しむことができ、授業が分かる生徒)ではなく、もとからできない生徒にフォーカスしていくべきではないだろうか。もとからできる子はほったらかしても勉強するのは明白なのだから、三年の選択授業も「キャッチアップ」や「やりなおし」のための授業があってもいいのではないだろうか。ついていけなくなるのは自己責任という態度ではなくて、落伍者を出さない方向にシフトしていくべきではないか。こんな選択授業はどうだろうか、「今更聞けない数学Ⅰ・A」。どうせ元からできる人間に授業したところで釈迦に説法といったところだろう。ならばHRと固定担任制を廃止して、1クラスに3人ぐらい担任をつければいい。国分寺高校は教員が70人以上もいる。24クラスに3人つければ72人。人員的な負担があるなら、進学指導を重点化したい3年生か出遅れを防ぐために1年生だけでもいい。その代わり毎週面談を実施すればいい。そこで学習の進捗状況を報告するのだ。自分の努力を言語化して他人に伝えれば、自分の頑張りを確認し教員から補助的なアドバイスをすることもできる。できる生徒は授業を取らないで自習して進捗を毎週報告する。できない生徒は少人数授業(それこそ10人ぐらい)で徹底的に質問することができるようになるのではないだろうか。我々の意見は授業が楽しくわかる人には有効。授業が退屈で分かりやすいと感じない人には向いてない。実に当たり前の話である。
各教科の学習法に対しても提言をさせていただこう。ただ、教員の労働時間はOECDの33か国中最下位という日本の学校労働環境であるから無理は言えない。ただ“創造的破壊”をする人材をするにはこんな教育が望ましいという話に過ぎないのであしからず。
まずは「英語を制するものは受験を制する」とまで言われる英語である。アンケートでも直前期の勉強法で断トツを占めたのは赤本であった。(広義の意味での解釈だと「あまりやらない」「リラックス」したといった意見が直前期は多かったが)そこで「アルゼンチン式勉強法」を提唱したい。なぜアルゼンチン式なのか。それは1978年、1986年と2度のW杯優勝を成し遂げたアルゼンチン代表を支えた、マラドーナ、ブルチャガ、カニージャ、ラモン・ディアスなどの名選手を育てたアルゼンチンの育成法になぞらえたものである。当時のアルゼンチンサッカー界の主な練習といえば、素走りと紅白戦だけ。現在のスポーツ科学に鑑みれば明らかに誤りである練習で、それでもサッカー史上に名を残すタレントを育てあげたのである。これを英語の勉強に言い換えれば、素走りが多読、紅白戦がスピーキング。直前期なら素走りが英単語で紅白戦が過去問。はっきりいってこれだけで十分ではないか。あの頃のアルゼンチン代表のようなタフな英語力が身につくだろう。そしてそれは大学進学後、英語論文を読む力になるのではないか。
次に国語科。国語教育は作文主義に移行すべきである。名作鑑賞会に終始し惰眠をむさぼる時間から解放され、授業準備から教員も解放される。作文といっても色々工夫できる。修学旅行に行ったら紀行文を書き、こもれびのあとにはエッセイを書かせる。『山月記』の巻末につける解説を長々と書かせた後には、『舞姫』の売り出しのキャッチコピーを25字程度で書かせる。『万葉集』を読んだら解釈を含めた解説文を書かせるのもよし。『論語』を読んだら現代のギャル語風に訳させてみたりするのもいい。余談であるが、アンケート回答者の年間平均読書数の推測値は10.6冊。さらに回答者の24%が年間読書数が0冊と回答した。もっと読書したほうがいいのではないか。どの情報媒体よりも情報のコストパフォーマンスが良いのだから。検定教科書に載っているような文科省の息のかかった文章読んでないで、村上龍とか筒井康隆みたいなしょうもない文章を読めばいいのである。それが真に高校生らしい読書である。
そして数学科。毎年多くの人が数学を嫌って3年時の選択で数学から逃れていく。一方で得意な人は嬉々として問題を解きまくる。要するにわかる人とわからない人の差が露骨にできる教科であるというのは周知の事実だ。私は「数学をあきらめちゃいかん」という学校教師の言に従い、最後まで数学に取り組んだが、センター試験では数学Ⅱ・Bの点数は47点であった。(筆者注:センター試験得点開示の結果、30点であったことが判明した)あきらめなかったが点は取れなかった。さらに数学の勉強法についてアンケートでも掲載できるような有効なアドバイスが得られなかったので、私から数学の勉強法について述べることはできない。
理科についても文系の私からは申し上げることはない。あえて言うなら地学は問題が難しくなりにくいのでお得であるということであろうか。
社会科について。歴史は逆からやるのがいいのではないかという漠然とした思いがある。史料に基づくという歴史学の原則ために近代以降、日本史は文化史の合間に権力者の交代が起き、世界史は半ば各国の文化史化してしまい、多くの受験生が受験を控える中で失速するのはよくある現象ではないだろうか。(偏見も多いが)では、歴史を逆から学ぶメリットはなんであろうか。ひとつは多くの大学は比較的近い時代から出題する傾向が多いからである。ふたつめは先述の挫折を防止しやすくなるからである。そしてもっとも重要なみっつめは、トヨタやマッキンゼーといった一流企業で徹底されている“なぜ5回”という知的関心の態度を身に着けるためだ。表面的は別の問題でもなぜ?なぜ?と原因を問い詰めていくと根本が同じ問題であることが多いのは、ビジネスでも歴史でも同じだ。世界のトップ企業で通用する、物事への態度を身に着けることができるようになるだろう。もっとも教員の負担は計り知れないが。
公民科は、より実生活に身近であるのだから、身近な事例との関連を見出せるようにすべきであろう。私の意見だが、年度初めの一年生の奉仕活動遠足をやめて、国会前にデモ遠足をするのがいいと思う。プラカードを一人一枚作り、「校庭を人工芝にしろ」とか「ウォシュレットをつけろ」とか「体育館にエアコンを」とか思い思いのことを書いて、民主主義をこの身で感じるのだ。先生方も「賃金あげろ」とか書いて一緒に行進して、公務員の争議行為は禁止だとか言われたら、「学習活動の一環です」といえばいいのだ。
ここでいささか急だがある男子生徒の声をお届けしたい。
匿名希望(48期)「一年のとき、生まれて初めて1という成績をもらいとてもショックを受けましたね。だけど、そのあと僕は学校の成績は自分の成長とは何らかかわりのない数字であると知りました。定期テストで点を取り、課題をやるということに意味がないとわかったからです。もちろん点を取るに越したことはありません。だけど定期テストで点を取るための勉強など価値がない、そう思いました。英語の課題は私は答えを映して提出していたのですが、もはや途中から提出することすらやめました。定期テストも大して点が取れなかったですが、実力テストの偏差値で見るなら私はそれなりの数字を残していました。別に塾には通っていませんよ。毎回の定期テストであまり点は取れていませんし、課題もやっていませんし、予習復習も大してやっていません。それでも自分の望む大学には行けました。正直授業をした記憶があまりありません。日頃の疲れからか寝ることも多かったです。家庭学習ですか?それはもちろんやっていました。けど、授業の準備という感じではなく独立した勉強という感じでしたね。夜に時間のない中部活で疲れて勉強することはつらかったです。授業の時間を有効に活用したかったとは思いますね。いや、それは授業をしっかりと聞くということじゃなくて。生産性のある時間にしたいという意味で。自主性みたいな。アクティブにやりたかったですね。なんというか、生きた勉強という気がしないです、授業は。あくまでも大学入試に向けた勉強というか、こちらが授業を有効に活用しようと思うと自分の力不足を思い知るんですよ。例えばなんですけど、世界史でフランス革命を勉強するじゃないですか。高校の授業レベルだとナポレオンは自由と平等を広めた。そして西欧の他国はその動きを阻止しようとした。となるじゃないですか。でも、そこで疑問がわくんです。本当にそうだったのかな、って。でも高校生の知識じゃわからない、調べようにも参考になる文献が見当たらない。本屋で探せばいいと思うでしょ?そうじゃないんです。本屋の本も自分では本当かどうかわかりませんよ。となると、自分の頭で推測するしかないんです。けどね、授業時間じゃ足りないんですよ。授業は受け身だから、自分で考えるより先に暗記事項を聞き取って覚えていくしかない。私なんかは英語の時間を減らして世界史に費やしてほしいなんて思うんですけどね。そうもいかないらしいです。文科省が定めているんです。コミュニケーション英語とか英語表現は必修だ、みたいに。そこは受け入れるしかないのかなって。少し話がそれましたが、そんな歴史を深く学びたいなら趣味でやりなよと思うかもしれない。でもよく考えてください。それでは歴史認識にずれが生じてしまう。今も問題になっているじゃないですか。慰安婦問題とか北方領土問題とか。要はあれは歴史認識のずれが問題なわけでしょう。日本は北方領土は日本のものだともちろん主張しますがロシアの教科書だとロシアの領土だと書かれているかもしれません。詳しくは知りませんが。そういう問題を目の当たりにすると簡単な認識では問題解決ができないことがわかります。そう考えると教科書や市販の本はおろか教師のことだって信じることができるでしょうか。完璧には信じられません。やはり本当のことを知るすべは限られてくるでしょう?だったら、自分が知るところがすべて事実であるというのを否定して物事を判断しなくてはならない。だから難しいんです。授業をするというのは。ならどうすればいいか、授業をしなければいいんじゃないですかと私は思ったりもしますが、現実的ではないでしょう。結局大学受験に走ってしまうのが現状です。だからつまらない。教員にはそれぞれ学んできたことがあると思います。それが見えた時だけ私は面白いと思います。だから、授業という型にはまってしまうのではなく、自身の気づきをわかりやすく伝える授業をしてほしいとは思いますね。高校生が何を偉そうに語ってるんだと思われるかもしれませんが。」
課題に関するところはのちにつながってくるがここでは触れないでおく。後半部分についてはまさに授業は神ではないという意味に捉えられるであろう。大学入試のための勉強には限りがある、だからつまらない。しかし、大学入試の範疇を超えようとすると、大学レベルの難しい問題であると、一蹴される。進学校なのだから大学入試のための勉強をするのは当然であると思うかもしれない。しかし、それなのであればもっと大学入試に特化した授業を行い、実績を出すべきである。現状はどっちつかずの中途半端な状況である。データからいえば、授業が楽しいと感じられれば入試には有利になるのだ。授業が楽しければ成果が出るはずだ。しかし、大学受験のための勉強がつまらないというのも事実。教員には楽しく、大学受験にも通用する授業を目指し、頭を悩ませてほしい。
ソビエト連邦崩壊から30年近くたとうとしている今でも、レーニンの言葉を引用する国分寺高校の教員が多い。もしこの言葉がレーニンのものだと知っていて、言っているのであれば彼らはマルクス主義者に違いない。知らないで言っているのだとすれば、それは恐ろしいことだ。おそらくその先生は、レーニン級の偉大な指導者に違いない。
たくさん勉強すれば、たくさん学力がつくのだろうか。我々は、労働生産性≒学習生産性と仮定して適切な学習量を分析してみた。また、本稿では「GREAT@WORK効率を超える力」(三笠書房/モート・ハンセン著、楠木健監訳解説)を大きく参考にしている。
オレンジを絞ってジュースを作るとき、最初は勢いよく果汁を絞り出すことができる、ある一定量絞り出すとほとんどでなくなり、最後には皮が擦り切れてきて、おいしくないオレンジジュースになってしまう。これを労働時間すなわち学習時間に言い換えると、週当たり学習時間は50時間まではたくさん果汁が出る状態といえる。つまり、生産性は上昇する。ところが50時間を超えると停滞しはじめる、仕事量に対する生産性が出がらしの状態だ。そして、63時間を超えると学習生産性は下降し始める。つまり、生徒には週あたり50時間程度の生産的活動に参加できるよう学校は設計すべきで最大でも63時間以下に収めるべきである。これには各教科と生徒の意見を交えたクロスファンクショナルな(組織横断的な)調整が必要である。
今回、我々は生産的活動を授業、部活、家庭学習(塾、予備校を含む)、こもれび祭準備の4つと定義した。例えば、あり土の週で国分寺高校で模範的な三兎を追っている生徒を仮定してみよう。週の授業時間が35時間!(3年間授業を受けたが改めて衝撃の時間である。これはフランスが週の法定労働時間が35時間というのを考えると恐ろしいことである。)に加えて、活発な運動部では一回2時間の練習が週6日で12時間。この時点で47時間である。ここにこもれび祭準備が3時間加われば、あと13時間分の生産的行為を行っても生産性の向上率はほぼ横這いである。
このことから「学年×2時間」という一日の家庭学習目標時間がいかに無謀かがよくわかる。要するに予習、復習、提出課題はほとんどが無意味なのだ。生徒の大半も事務作業としてこなしている。
教材選定も教員だけでなく、生徒、OB会、PTAも含めた4者で行うのが適切ではないか。現状では買わされるがままで使い勝手は悪くて、答え写すだけの事務作業化は著しい。多くの人が感じていることだろうが、そもそも学年全員一律同じ課題をやるというのが非合理的なのだ。自分の課題を自分で設定するのがベストだろう。教員は提出を強要するのをやめて、生徒の学習量の設定のサポート役にしふとすべきではないだろうか。前述の『GREAT@WORK効率を超える力』では、情熱を目的と一致させられる人は、目的と情熱のどちらか一方または両方が欠けている人よりも、平均して業績がはるかに良かったことが述べられている。国分寺高校の生徒には情熱にあふれた生徒が多いにもかかわらず、教員が東京都教育委員会からのプレッシャーで課題を大量に出し目的を見失わせ、情熱と目的が一致させられないのは嘆かわしいことである。
私は国分寺高校は従来の進学校の枠をブレイクスルーして、“創造的破壊”をできる人材を育てる学校へとシフトチェンジするべきだと考える。そこで参考にするべきは国公立大学合格者数を20倍に増やし“堀川の奇跡”と呼ばれた京都市立堀川高校がいいのではないだろうか。
以下は日本経済新聞電子版2017/10/22付 出世ナビ「学校のリーダー普通の公立高が大化け 京大合格率上げた堀川の探究科京都市立堀川高校の恩田徹校長に聞く」からの引用だ。
堀川には週2回、探究基礎という授業があるが、1~2年生は相当の時間と労力をこれに費やす。10月10日、堀川は秋休みだったが、校内の自習室にはたくさんの生徒がいた。高校3年生の女子生徒に探究基礎について尋ねると、「地学ゼミに入り、カミナリの研究をやっていました。ピカッのあれです」とニコッと笑ってこう答えた。
日に焼けた高校1年生の男子生徒は、「宇宙関係の探究基礎をやります」と話す。この生徒は「ぜひ探究をやりたい」と考え、中学3年生のときに堀川の恩田徹校長にわざわざ話を聞きに来たという。宇宙分野の探究をスタートして「京大の物理工学科に進みたい」とすでに志望大学と学科まで決めている。
恩田校長は「探究とは、簡単に言うと、知りたいことをどんどん探っていくことです。1つのことを探究していくと、高校のレベルで止まらず、大学の水準も突き抜ける。それを我々はサポートするだけです。一方で大学入試のための勉強もガンガンやります。あえて二兎(にと)を追うのです」という。
秋休みにもかかわらず、自習室にはたくさんの生徒がいた
堀川の授業は前期と後期に分かれている。10~12日はその中間の秋休みだ。入学すると、まず自らが何を探究するかを考える。前期には研究テーマの設定の仕方や、活動の進め方、論文の書き方、参考文献の引用のやり方など、探究の「型」を学ぶ。
後期から9つに分かれたそれぞれのゼミに入る。ゼミは国英数や物理、化学など従来の科目に即した形で構成されるが、1年の1~2月ぐらいに研究テーマを徹底的にもむ。ポイントは「絶対にオリジナルの研究テーマでなくてはいけません。大学の研究論文かなんかのコピペではダメです」と恩田校長は強調する。(以下略)
探求基礎で生徒たちは研究の仕方を学ぶという画期的なアイデアが堀川高校は従来の教育にイノベーションを起こしたわけだが、国分寺高校はほかの高校の真似に終始してはいけない。
新入生はオリエンテーション期を目一杯に使って知の技法を学ぶ。具体的にいうと、スケジュール術、ノート術、アイデア術、プレゼン術の4本の柱だ。ノート術は『頭のいい人はなぜ方眼ノートを使うのか』(かんき出版)の高橋政志さんやブラック企業アナリストの新田龍さんを呼んでほしい(あくまで願望だが)。なぜ、知の技法を学ぶ必要があるのか。例えば東京から大阪に行かなくてはいけないとなったとき、いきなり自転車をこいで向かう人はいない。(キャノンボールと称して24時間で行ってしまう人もいることにはいるが)お金を工面して新幹線に乗るだろう。そのほうが時間対効果がよく、快適だからだ。ところが殊勉強になるといきなり全力でスタートしようとする人が多く、教員もそれを助長する発言をしてしまう。ただ純粋に努力をすればいいというものではない。
松下電器創業者松下幸之助氏(1894-1989)のこんな言葉がある。「額に汗することをたたえるのもいいが、額に汗のない涼しい姿もたたえるべきであろう。怠けろというのではない。楽をする工夫をしろというのである。」まさしく。
これは筒香が横浜高校で野球をしていたころに重要だと思っていたことだという。彼はインタビュー内で「勉強にしても高校のこともあるので大事に思っていましたし、遊ぶ時間を削ってでも、矢田先生(矢田接骨院・院長)から教えていただいた体操をすることを大事にしてきました。(『高校野球ドットコム』より)」と語っている。我々は学生にとって勉学が最優先であるとただ唱えることは無責任だといいたい。優先事項は自分で考えさせるべきである。その点、森先生は野球部に「野球のために勉強しろ」という趣旨の発言をされていた。何でもかんでも勉強が最優先というのではなく、勉強もやるが部活もやるということができる環境づくりを進める必要があるのではないか。その中で軸となる優先事項が必ずあるはずである。勉強からの切り口だけでなく部活から始まる勉強の可能性も視野に入れるべきであるのだ。
そのうえで現状、各部活の使用可能範囲が狭いという問題があるが早急に改善すべきであろう。特に陸上部やサッカー部などは外部での練習を強いられている。これでは帰りが遅くなり勉学やほかのことに使う時間が限られてしまう。まずはグラウンドの拡張を行うべきである。また、夜は暗いために球技系の外部活はボールが見えなくなるなどの問題に悩まされている。ナイター設置の動きがあったとうわさには聞いたが実行は依然されないままである。生徒の安全面を考えると早急にナイターを設置する必要があるだろう。また、トレーニング器具についてだが、最近の高校レベルのスポーツでは器具を使ったトレーニングを有効に行い、時間的にも効果的にも効率の良いトレーニングを行っている。都立高の予算では厳しいのかもしれないが、効率よく練習が行われれば勉学やその他の活動にも時間を割くことができる。その点からいって最新のトレーニング器具を用意することは、最優先事項であるといえる。また、野球部やサッカー部は昨年の成績からいえば全国を狙える位置にいるといえる。その他の部活も学校の努力によってより優秀な成績を残せるのではないかと思う。勉学にも力を入れていく中で、部活にもより力を入れていく必要があると感じる。よって校庭を芝生にする。そうすれば、こもれび祭の体育祭の安全も確保できるであろう。部活に力を入れるとなると、当然教員に重い負担がかかることも懸念される。そもそも教員が顧問をやるというシステムがおかしい気もするのだが、その点はようわからん。教員よ、不謹慎たれ!とでも言っておこう。
改善するべき点
・ナイターの設置
・グラウンドの芝生化
・グラウンドを拡張
・格技棟のの建て替え
・教員の負担減
〈夏の過ごし方〉
状況は大体4パターンにわかれる
1、勉強とこもれびの両立
2、こもれび一択(勉強したくてもできなかった)
3、ガチ勉強(こもれびやってて10時間勉強してる猛者もいた)
4、部活優先
内容は基礎固めや苦手克服を重点的に行なっているものが多かった。一教科を軸にやるといいという意見もあった。
夏は受験モードという人が多いのかなと思った。こもれびに時間を費やす人は限られている状況だと思われる。サッカー部や水泳部は部活が終わってないので結構厳しい状況だと思うが、部活+こもれび+勉強をこなしてるという人もいたから不可能ではないのかなという感じ。普通は無理な気がするけど。
〈直前期の過ごし方〉
【勉強の仕方】
集中できないときはやらない
時間をはかる
暗記系科目は最後でやる
英語などは感覚を失わない程度にやる
過去問をひたすらやる
今までやったことの復習をする
電車など移動を活用
学校の講習はいく
飽きたらやめる。飽きるのに飽きたら飽きるのをやめる。
【生活面】
学校に来てモチベを保つ
生活のリズムを崩さないように意識する
友達と話すことで精神を保つ
息抜きは適度に入れる
毎日10時に寝てた生徒はストレス性の腹痛はあったけどウイルス性ではなかったそうです。報告ありがとう。よかったよかった
メンタルを鍛えまくる
〈使った参考書〉
〔英語〕
【単語】
英単語ターゲット
単語王
チャンクで英単語
システム英単語
東大英単語
【熟語】
解体英単語
鉄壁
【長文】
ポレポレ英文
読解標準問題機構
【文法】
パワーステージ
構文150
【和訳】
英文和訳演習(駿台)
【その他】
上智の英語
〔国語〕
【現代文】
現代文読解力の開発講座
国語の語彙集(桐原書店)
【古典】
30日完成 古典
ゴロゴ
パワーアップ古文
極める古文漢文
漢文ヤマのヤマ
〔数学〕
大学への数学
メジアン
チャート
プラチカ
河合の大学入試厳選
教科書
最高の演習
〔理科〕
【物理】
名門の森
物理のエッセンス
重要問題集
【化学】
化学の新研究・新演習
化学重要問題精講
重要問題集
【生物】
生物の良問
資料集
大森徹の生物基礎
〔社会〕
【日本史】
日本史実況
30日スピードマスター
日本史標準問題精講
【世界史】
ウイニングコンパス
時代と流れで覚える世界史B用語
早稲田問題集・山川出版社
増元先生の作品たち
【政経】
東進・一問一答
【現社】
面白いほどわかる現代社会
この発言は資本主義社会において商業価値を生み出す全ての生産に一切の美を見出さないという発言であるが、この発言から考えると文化祭における創作が美しくあるためには、見返りを求めてはいけないのである。変な言い方をすると最も優れた作品とは、最も意味の無いものであるということなのだ。この矛盾こそが、木もれ陽祭の1番の敵であると思うのだ。すなわちこの事実を無視してしまうがためにアンチが生まれ本当の意味での一体感を感じられなくなってしまうのでは無いだろうか。まずはこの事実を受け止め、その上で無価値が生み出す美をどうにか追っていく必要があると思うのだ。しかし、木もれ陽祭において美を生み出すのには至らない点がいくつか見受けられる。そこで我々は現状を把握・分析し、本来あるべき木もれ陽祭の姿を考察しようと思う。
一つ言っておきたいことがある。我々は各所に批判的な文章を書いていくが決して文句を言っているのではなくこんなところを改善したらどうかという提案である。もっといえば、あなたが文章を読んで何か引っかかるところがあれば、そこが我々とあなたの差なのであり同時にリーダーと平団の差ともいえるのではないかと考える。いわば、感覚の違いである。そういった共通認識の差に問題があるのかもしれないとも思う。ひとつ、我々の書いた文を読んで引っかかりを感じたのであれば、まずは自分を顧みてから改善すべき点を見つけてほしいのである。他者に何か要求するのはそのあとである。
原則
リーダー…団長、チアリ、援団
平団…リーダー以外
こもうん…運営する人
アンチ…明確な定義はない。非協力的もしくはリーダーに批判的な輩
「」もしくは・ …アンケートからの引用
としておくが文脈で判断してほしい。中には平団という呼び方を好まない者もいるみたいだが、申し訳ないがわかりやすいので使わせてもらう。まあ、平団は一般職、リーダーは管理職とでも言っておこう。(好まない理由がよくわからないのだが、ミスコンが差別的な表現を避けるために中止になったのと同じ類ではないかと推測したりもする。もし本当にそうであるのならばぜひ差別的表現のない世界を作り上げる努力をし続けてほしい。)
さて、まず我々は現状の問題について考えた。三年間、木もれ陽を一番近くで眺めた我々が考えたのはアンチこもれびとそれをそういうものだと割り切るリーダーについてだった。ここで、各々それぞれの立場から思うことがあるとは思うのだが、まずはどうしてそんな状態になってしまうのか考えたい。
理想とビジョン
これは主に団チア、援団に言えることだが、アンケートを総じて見たときに団チア側のイメージやビジョンが平団その他に伝わっていないケースが想像できる。イメージは言葉を通して伝わるものなので、全く歪められずに伝わることはない。だから難しいのだが、それならばイメージの共有の仕方を形式にして固めた方が良い。それがノウハウの蓄積である。例えば、現状では平団の役割は仕事を手伝うことのようであるが、仕事とはなんなのか。後述の➁とつながってくるが何が生まれるかもわからない労働など平団からすればやる意味を見出せないのは当然である。団チアや援団のイメージ、創作の完成形が平団に理解できてからやっと労働は始まるのだ。だから、完成形を共有する方法を考えたほうが良いのである。その方法として話し合うという方法がありそうだが、ただ話し合うのでは何も進まずに終わるというのがおちだろう。最近の都立入試では集団討論なるものがあるみたいなので、それをかいくぐってきた強者には力を発揮してもらいたいところである。会議をしない会社というのが存在することかわかるように話し合いは必要不可欠というわけではないようだ。報告・連絡・相談を一切なくした会社も存在する。成功するビジネスマンは上司に何も告げずに契約を取ってしまったりもするそうだ。それらの根幹を突き止めれば何かわかってくるだろうと思うのだが、話がそれそうなのでやめておく。ビジョンや理想がしっかりとしていれば方法は問わないということを伝えたい。
②見返りのない創作
冒頭では「美」と表現したがこもれび祭に捧げたものは実体を持ったものとしては帰ってこず、別の意味を持つものだ。だからこそ美しいのであり感動するのだ。しかし、目に見えないのであれば当然追うのは難しい。だから非協力的な平団というのは必然的に出てくるものなのだ。ではどうすればよいのか。これから少しずつ探っていこうと思う。
<避けられない対立~平団vs援団~>
アンケートでは、
・リーダー(援団、団責、実行委員)に求められる能力・運営の方法、ノウハウ・計画の立て方
・平団に求められる積極的参加の方法
の二点を聞いたが、質問からリーダー・平団への不満や要求を取り上げそれらの批判からそれぞれ反省すべき点と課題、できれば解決策まで考えていきたい。今後の活動に役立ててほしい。
リーダーへの要求や不満
①当たり前のこと当たり前にやる。
アンケートに集められた記述をそっくりそのまま引用する。
・まわりのことにも目を配ることができる人
・自らの機嫌で回りを振り回さない
・時間を守る
これらは言わずともリーダーに求められる能力の欄に記載されていたのだが、リーダーという以前に人として、社会人としてできていないとおかしいことのはずである。これはリーダーができていないということなのか、それともまあ当然だけどという枕詞付きのものなのかは分からないが、当たり前のことを当たり前にやる力というのが求められそうだ。とはいえ、それが難しいことであるというのも平団は特に忘れてはいけない。できていないことを無能というのではなく、寛容な姿勢で受け止めることもまた大事であると思う。また、当たり前のことを当たり前にする、これは平団にも求められるということを忘れないでほしい。そういった最低限をこなすような上手なアンチのやり方講座でも開きたい。ブラック企業アナリスト新田氏を呼び上手なこもれびの避け方を教えてもらおうと思う。
以下リーダーに求められる能力あたりまえシリーズ
・団全体をまとめる力
・ビジョンを持って揺るがない
・一か月、二か月先を見越してスケジュールを組む
・馬鹿以外
・積極性
・こもれびが終わるまでのことを常に見通せること
②団全体をまとめる
団全体をまとめるということもリーダーには必要である。しかし団全体をまとめるというのは難しい。そもそもそんなことできるのか。疑問である。「約40人をまとめるのはかなり至難の業。もちろんクラスの中にはグループも存在するわけだから、偏ったグループからの人選だとさらにまとめにくいと思う。」という記述があったのだが、前半は前述のとおりやはり団よりもさらに小さいクラスという単位でさえまとめるのが難しいということである。考えるべきは後半の記述である。偏ったグループからの人選、正直よくわからないが女子っぽい問題であろう。安倍晋三のお友達内閣みたいなものであるかわからんが、もしかしたら安倍晋三は女の子なのかもしれない。本気でこもれびに向かうなら、偏った人選は避けるべきだ。選び方を提案するとしたら、例えば団長チアリが決まった時点で二人で相談し、クラスのグループや状況を考慮して慎重に援団を指名していくやり方があるだろう。この時に大事なのは「私たちはこういうことをやりたい。こういう人材が必要だから、あなたにこういうことをしてほしい。」と伝えてから相手にその役割を引き受けるかどうかの判断をゆだねることであろう。こうすれば、「仕事をふる」、「人に頼る」、「人を使う能力、人に頼る勇気」といった要望も難なくこなせるはずだ。平団に対してもしっかりとこれができればビジョンの共有が果たせるのではないか。でもそれにもやっぱり難しいものがある。また、下級生をまとめるということも難しい。筆者自身、一二年次は三年のまとめ方の文句を聞き、三年次は下級生のやる気のなさの文句を聞いてきた。そこで、下級生と仲良くなる方法を一つ紹介したい。「後輩にいかになめられるか。⇒自分のプライドを捨てて後輩に馬鹿にされると仲良くなりやすい」だそうだ。人柄もあるだろうが、確かに後輩にいじられるようなやり方は有効かもしれない。でも、威厳を完全に失ったリーダーはここぞという場面でバシッと決められなくなるかもしれない。「時々の厳しさ」、「いかに多くの人間を巻き込めるか」「馴染めていない子がいたら話しかけたり、周りをよく見る」、「陰キャも楽しみたい」という要望に応えていく必要があるなかで、やはりそのあたりはリーダーの力量に任されてしまうのだろうか。
また、団をまとめるうえで、スケジュール管理ということが欠かせない。筆者自身のクラスはスケジュールの管理がある程度はできていたと思うが、平団にとってみると劇メンバー、援団が何をやっているのかわからず自分が何をしていいのかわからない場面が多かったように思える。スケジュールがわからなければ平団も仕事ができない。全員に今だれがどこで何をしているのか伝わる必要がある。またそれが難しいのであろう。三年になると塾に通う多くのまじめな生徒が勉強を理由に学校に来ないといった問題があるからだ。リーダー側には一二年から塾を理由にしている方は最難関国公立や医学部志望だと思うので、慮る必要があるだろうが、三年もとてもがんばってその他の事情を全て廃して血の滲むような猛勉強をしに塾に通っているので目をつぶったらどうかと言いたい。かといって学校に来ない輩が多いのなら仕事をできない。「頑張っている人がいることを忘れない」「リーダーは思った以上に大変(見えないところでもたくさん仕事ある)ので少しの気遣いや楽しんで参加する姿勢がみられるととてもうれしいと思う。」「前に立つ人の気持ちを考える」といった意見がある通り、平団にそういった他人の事情を推し量るような想像力が必要である。しかしそれが難しいときリーダーは自分たちでどうにかしなきゃいけない。そのように平団がリーダーの気持ちを推し量ってくれない状態があるならば多少の強制力は必要なのである。しかし、強制の仕方は考える必要がある。例えば、どうすれば解決できるだろうかと考える前にまずはビジョンがあるのかどうか考える。何度も言っているが、大事なのはビジョンである。ビジョンが見えていれば平団の役割をリーダー側で決められるはずである。まずはビジョンを言語化してわかりやすく伝えること。そうすれば多少の強制も平団は受け入れてくれと思う。わかり辛いかもしれないので具体化してみよう。「私たちはリアル野球盤を文化祭で行いたい。校庭を使うのだが、問題はどうポイントを数えるかである。今のところは板を用意してポイントを書きグラウンドにちりばめる予定なのだがほかに方法がないか考えてほしい。明々後日までに二つアイデアを出してほしいのだがどうか」これならば、多少の強制はしているが受け入れやすいだろう。最初に何をやりたいかつまり、ビジョンを明確に示しているし、何をしてほしいかも明確だ。無理もない。想像力の豊かな人に頼めばもしかしたら二つと言わず10個以上アイデアを出してくれる可能性だってある。ただ、こういった方法で準備を進めるなら優秀なブレーンが必要かもしれない。何がどこで行われているか把握し的確に計画を進めていく必要があるから。つーか普通に考えて優秀なブレーンは必要だろ。スケジュールに関してもビジョンを持てば大体いつ何ができていなければならないかわかるだろう。平団全員にまで情報が伝わらないのならラインなどを使って伝えればいい。ただ、アンケートの意見にもあったが「ラインだけでやり取りをしない」というのは前提だ。グループラインでは相手に伝わったかどうかわからないし個人ラインでは誰に何を伝えたか把握できなくなる可能性がある。しっかりと伝えたいなら直接伝えるというのが一番である。話がそれたがスケジュールは大体の計画が決まったら多少遅れてもしっかりと勧められるように無理なく組むことが必要だ。「しっかりとした予定を立てる(3年は有効に時間を使わないとイライラしちゃう人が多い)」「計画を立てるのは大変だったから、何人かで手分けしてやったほうが良い」といった意見もある通り計画の立て方の見直しも行うとよいだろう。ラグビー日本代表監督のエディー・ジョーンズは彼の著書『ハードワーク』によると、シーズン中に50回に近くスケジュールを書き換えるそうです。エディーさんはそれを健全なことだとのべています。皆さんの計画は健全だろうか?計画の立て方というのは研究してほしい。
平団への不満・要求
アンチというものは必ずこもれびに降りかかる問題ではないか。人によってアンチのとらえ方は異なると思うが、アンチとは何なのかを整理して現状を把握する。
まずはリーダーが平団にどんなことを要求するのかをみてみよう。アンケートでは自主性を要する意見が多く見られた気がする。例えば、
・平団・援団ともにやることが見つからなくても「自分に何かできることある?」の一言で変わると思う。
・自覚を持つ
・指揮をしている人の話に従うだけでなく、自ら何かできることはないかと探す
・いかにリーダーの気持ちを汲み取れるか、感受性と思考と推察力
・自分からリーダーにやるべきことを聞きに行く
・アンチはアンチなりに少しでも仕事を見つけてほしい
これらの意見は平団に自主性を要求するものであるが、そもそもアンチにやる気がないってことが問題なら自主性を求めることなんて無理があるのではないか。いかにしても平団に自主性があればこれらの意見は大事かもしれない。しかし、もともと平団にビジョンが伝わってないから平団にとってやるべきことがわからないのだ。何よりまずビジョンを明確にしろと言いたい。
また、平団は「受け身にならない」ことが重要であり「自分のできることは積極的にやる」こと、「周りを見て何をすべきか見極めること」、「部活で忙しくても誠意を見せる」、「忙しくても協力したいという態度を示すこと」を重視する必要があるという。「」の部分はアンケートの記述であるが、これらを平団に求めるということ自体間違いである。平団は想像よりも手ごわいのだ。それをしっかりと認識してほしい。実は筆者自身は三番目の「」の方法を活用したのであるがその話は置いておく。
とはいえアンチの強さをしっかりと認識した発言も見られた。「マイナス発言をしない」、「別にやる気なくたっていい、けど全体に迷惑をかけるのはやめろっていう意識づけ←練習でなくたっていいけど全体合わせのときに何もできなかったり」、「○団会(ふりを覚えるやつ)にはいく」、「予定を知る」、などは、比較的ハードルを下げた意見といえる。また、受け身でもいいから参加してほしいという旨の発言も多く見られた。「頼まれたときに快く引き受けてあげること。できなくてもその旨をきちんと伝えること。めんどうくさいからはなし」、「リーダーから働きかけられたときに応じる」、「アンチにならなければなんでもいいのでは、適当にこなすだけでも全然いいと思う」といった意見は消極的でもいいからたのむわという負担の軽さでここまで来ればハードルもくぐれない高さにまで下がるだろう。
「団チア、団責に思うことあるならマジではっきり言わないと奴らは6に動かない」「リーダーとか上に立つ人に思うことがあればいう」というように、リーダー側に平団ならではの不満を‟はっきり“いうことが必要であるかもしれない。でないと、リーダー側が問題解決のしようもない。文句だけ言って何もしようとしないケースがかなり多くみられたように思うが、ただ文句を言うというのは、自己満足でありただのわがままである。はっきりということの重要性は平団側に認識してほしいものである。
<その他気になった記述>
【その場の一体感】
「まわりの状況をしっかり見つつ、場の雰囲気を良くし、一体化させること」
一体感とはなんであろうか。我々はこの場合、一体感とは幻想であると考える。どういうことか。そもそも一体となるというのはみんなが1つになるということである。こもれびのレベルに置き換えると120(40×3)人が1つの塊、集団となるということである。これが本番で感じられたのならそれは感動することであろう。しかしここで言われているのはその場の一体感である。その場の一体感を重視するというのは、ただその場を取り繕っているだけというのに過ぎない。その場の雰囲気を良くすれば良い作品が出来上がるという幻想を抱いているのだ。ときには、場の雰囲気も悪くしてでも言うべきことをいうこと、それがイメージの共有に繋がるのではないだろうか。まあそれが難しいんだけどね。
【ミクロ・マクロの視点】
「ミクロ・マクロの視点を持つ」という記述があった。たしかにクラス全体で作り上げるものと個人的な役割を比較したときに、併せて考えるということが重要である。難しいかもしれないが、これもまずビジョンを明確にすることで個々の仕事が全体の創作に帰結していくイメージを持てると思う。
【洗脳的崇拝】
洗脳的崇拝というと、戦時の日本のような戦勝のみをよかれとする考え方の浸透などが思い出されるであろうか、詳しいところは勉強しないとわからないが、確かにそういった信じ込ませるようなやり方は有効かもしれない。ただ、こもれびという場でそれを可能にするアイデアは我々には思い浮かばない。リーダーが圧倒的カリスマ性を備えていてクラス全員をその雰囲気にさせればできなくもないか。めちゃくちゃ興味を引き付けるような創作のアイデアを考えるというのも可能性としてはありそうだ。かなりの工夫が必要だがやれなくもなさそうである。
【与党は正義か】
「キレすぎずに注意すること、熱くなるととにかく批判しまくるから(野党みたいにね)」という記述があった。野党をとりあえず批判するネトウヨの典型かと思ったので、我々は対案を出すことで先回りしてネトウヨに絡まれないように意識した。最近は右翼と左翼が何なのかも複雑だが。政治の話は水掛け論に終始することが多いのであまり不確実なことは言えないのだが、これはスポーツに例えられると思う。野球を例に出すが、プロ球団のファンは自分が応援しているチームの選手が不甲斐ないプレーをするとヤジを飛ばす。これと一緒である。ヤジを飛ばさないと選手は気の抜けたプレーばかり見せることだってあるのだ。ファンは球団に期待しているからこそヤジを飛ばすのだ。そして、選手を鼓舞するのだ。それが与党となると我々の税で飯を食う議員である。責任をもって仕事をしてもらわなきゃならない。それに批判するのなら立場上、野党の人がやるしかなくないか。そういうことも考慮しての発言だったのならなおさら質が悪いと思う。
<理想のこもれび>
ここからは我々がこんな木もれ陽だったらいいのになというのを書いていく。
【合唱祭】
コンサートホールの使用をやめて、野原で歌う。審査を撤廃し、最も小鳥が喜んだクラスの人の幸福度は高い。校内で審査をしたところで意味は感じない。無駄な争いはせずに合唱ができる喜びを感じよう。よって、競争が不要になったので課題曲も廃止する。
【低クオリティな文化祭】
文化祭はこもれび祭の一部で毎年多くの人が訪れるイベントであるが、内容に関していうと面白いアイデアで埋め尽くされたものとはいいがたいのではないか。三年生の劇は毎年圧巻であると思うが、一年生、二年生はどうだろうか。まず、一年生がレク、二年生が飲食店か短い劇のどちらかに絞られているというのがおかしいと思う。そもそも三年になれば劇を行うことは決まっているので二年で劇をやる必要はない。練習という位置づけかもしれないが三年になれば嫌というほど練習するはずである。出し物を限定してしまうとアイデアが妨げられてしまう。また、地域との連携や民間との連携を図るべきである。
☆一二年展示案
イ) リアル野球BAN(雨:ヘッドスライディング大会)
ロ) 鉄道ジオラマ
ハ) 接骨院
ニ) マグロ解体SHOW(回転寿司)
ホ) 模擬裁判(昔話裁判)例:桃太郎の鬼退治は鬼の生存権侵害になるか否かの上告
へ) プールで海戦ショー 例:トラファルガーの海戦、日本海海戦
ト) テニスコートでゲートボール大会
チ) 日焼けサロン
リ) ツイッターレスバトル
ヌ) 動物触れ合えないコーナー
ル) パチンコ&スロット
ヲ) プロ野球、競馬、為替予想会
ワ) 裏入試相談会
カ) 選挙演説対決
ヨ) わらしべ長者チャレンジ
タ) 精神と時の部屋
レ) 座禅寺
【スポンサー】
各企業から広告料をもらって、電通にスローガンなど考えてもらう。
ソフトバンクにペッパーを借りる
セグウェイを置く
TOTOのショールーム
にしこくんをを呼ぶ
【飲食】
生徒はやらない、民託にする。
・ミスタードーナツ
・丸亀製麺
・バーガーキング
・サーティーワンアイスクリーム
・わたなべ惣菜店 など
【ノリだけの中夜祭】
今のノリだけで行う中夜祭はいまいちである。中夜祭で必要なのは人を熱狂させる術を知ることである。ロックスターのデヴィッド・ボウイやローリングストーンズのミックジャガーはドイツの独裁者アドルフヒトラーの演説を研究したという。そこで私たちは中夜祭実行委員にはヒトラーの演説を研究させ、「わが闘争」の読書を義務付ける。また、学校の体育館では前回のように音響に不備がみられる可能性があるので、中野サンプラザで開催する。また昨今は刺激の強いものは未成年には教育上問題があるといって排除される傾向がある。しかし、本来はそういった強い刺激を受けながらひとは成長していくのだと思う。そこで、我々は格技棟爆破解体ショーを提案する。よって、中野サンプラザからパブリック?ビューイングという形で解体ショーが行われることになる。また、体育祭はさいたまスーパーアリーナでの開催となるが、中野サンプラザから約23キロ、糸井校長を乗せた神輿を担ぎ、約5時間かけて行列を作って移動する。これが本来あるべき中夜祭の姿だ。
【いつからか校庭開催になった体育祭】
以前は立川で行われていた体育祭だが我々が1年の時に中止になってからそもそも立川での開催が予定されもしなくなってしまった。いろいろな事情があると思うのだが、前述のとおり、それならばと我々はさいたまスーパーアリーナでの開催を提案する。また、競技には棒倒しを追加する。これで確実に体育祭は盛り上がるだろう。また、最近は危ないという理由で組体操が消えつつあるそうだ。確かに危ないからなくなってほしいものだ
私は生徒会を「ぶんじの宮内庁」と呼んでいる。儀式と会計しかしないからだ。私が高校入学前はもっと国分寺高校は自由な学校だと聞いていたが、年々厳しくなってきている。これに対して、生徒会は学校側と毅然とした態度で交渉するべきである。例えば、こんな事例がある。かつて合唱祭の日も髪染めが許容されていた。だが、オリンパスホールで合唱祭を行った際に、金髪、茶髪の怖いお兄さんたちがいると、学校へ連絡があり以後厳格化。これを許容していたら、直に何もできなくなって平凡な都立高校に成り下がるだけである。生徒会は全共闘よろしく激しく抗議して生徒の権利を守るべきだ。学生運動のように制服の着用義務をなくすとかやってほしい。それが生徒会の本義であろう。生徒会に対して言いたいことは以上。労働組合の重要性が身に染みるような働きを期待したい。
今回の調査ではセンター平均得点率は76.7ポイントであった。これからは様々な物事とセンター得点率の関係を見てみよう。
まずは登校時間である。15分刻みで調査をしたところ、最もセンター得点率が高かったのは7:15-7:30いわゆる朝練時間帯に登校する生徒は79.1ポイントで最も強かった。一方、最も弱いのは8:45-9:00に登校したいわゆる遅刻組であり、73.8ポイントと平均から約3ポイント低かった。つまり、朝遅刻する人間は自律できていないために勉強で成功できないというわけだ。だが、産経ニュース2015年11月4日付の「思春期は夜型、早起きは負担? 海外では始業時刻見直しも」と題した記事もあった。以下引用しよう。
米国小児学会が昨年、青少年の睡眠不足解消のために中学校と高校の始業時刻を遅らせることを推奨する声明を発表した。児童期から思春期にかけては生体リズムが一生の間で最も夜型化するとされ、日本でも始業時刻を遅らせるべきだと指摘する専門家もいる。(加納裕子)
“19~21歳でピーク
「思春期は体内時計の夜型化によって早寝ができなくなっている。気合だけでは早寝早起きは難しい」
10月、神戸市内で開かれた「日本子ども学会」学術集会で、講演した国立精神・神経医療研究センター部長の三島和夫医師(52)はこう断言した。
三島医師によると、子供は小学校低学年から徐々に夜型化し、男性は21歳、女性は19・5歳で夜型化のピークを迎える。その後は徐々に戻っていくが、学校の始業時刻に合わせて起床しなければならないため眠りが分断され、十分な睡眠時間が取れない子供が少なくないとみられる。
三島医師はこの集会で、米国小児学会が昨年8月、「中学校と高校の始業時刻を午前8時半以降に遅らせるべきだ」とした声明を紹介。「日本の高校生の8割が日中に眠気を感じており、1時間から1時間半、始業を遅らせることで救われる子供は多い」と、始業時刻見直しの必要性を訴えた。
集中力が改善
日本の思春期の子供たちの睡眠時間は国際的に比較してかなり短く、米国疾病管理予防センターが推奨する睡眠時間を大きく下回っている。米国の子供たちの睡眠時間も短く、米国小児学会は声明の発表に際し、「高校生の87%が、推奨された睡眠時間を下回っている」と指摘。しかし、午前8時以前に始業する学校もあり、8時半以降に始業する高校はわずか15%だったという。
こうした状況を踏まえ、欧米では、始業時刻を遅らせることによる効果を実証するための社会実験が行われている。
米国では中高生約200人が始業時刻を午前8時から8時半に30分遅らせたところ、睡眠時間は7時間7分から7時間52分と45分間長くなり、授業中の居眠りや集中力が顕著に改善。英国でも現在、約6万人の生徒の始業時刻を午前10時まで遅らせる試みが行われており、一部を対象とした研究では、成績上位者が増えたという。“
気合より科学的知見にもとづく。近代的理性主義的に行きましょうよ。検討してみてください。
次に、星座別のセンター得点率の順位である。私から一言ずつコメントさせていただいた。な
1位 いて座 80.0ポイント
…平均より4ポイント近く高いという圧倒的成績で優勝。もはやいて座のためにセンターがあるといっていい。
2位 みずがめ座 79.5ポイント
…平均よりおよそ3ポイント高い成績で次点。ぜひみずがめ座の人は心に余裕をもってセンターにのぞもう。
3位 やぎ座 79.4ポイント
…タッチの差でみずがめ座に敗れるも強さを見せる。来年あたりに頂点をつかみそうな予感すらする。
4位 おうし座 78.8ポイント
…表彰台にこそ立てなかったが平均におよそ2ポイント差をつけたのは十分な勝利といえるだろう
5位 ふたご座 77.5ポイント
…4位に1.3ポイント差と後れを取る。おうし座の受験生が多そうな大学に出願する際は気を付けほしい。
6位 さそり座77ポイント
…平均点を上回った最後の星座になるも、プロ野球なら最下位である。戦力補強が望まれる。
7位 しし座 75.83ポイント
…ついに平均を下回ってしまった。箱根駅伝なら来年は予選会出場しなければいけなくなった感じであろうか。
〃 うお座 75.83ポイント
…なんとまさかの同率である。テレビの星座占いでこんなことがあれば大バッシング間違いなしである。
9位 てんびん座 74.0ポイント
…平均から2ポイント負け越し始めてしまった。センター利用で大学を抑えようなど思ってはいけない。
10位 おひつじ座 73.5ポイント
…敗戦処理投手にような雰囲気すら感じるのは、私だけだろうか。地区予選レベルの星座である。
11位 おとめ座 72.5ポイント
…おとめ座の皆さんは申し訳ないが国公立向きではないのだろう。親に頭を下げて私大を受験してほしい。
12位 かに座 71.3ポイント
…平均に5ポイント差という無残な敗北である。サンプルに偏りがあったと思う人もいるかもしれないが、負けは負けである。素直に負けを認めて出直してきてほしい。
優勝はいて座。センター試験のジョコビッチと呼ばせていただこう。おめでとう。
朝ごはんの調査も興味深いデータが出た。朝ごはんを食べない人は平均を2ポイント以上下回る74.5ポイント。朝ごはんを食べない奴は論外である。遅刻してでも食べるべきであろう。さらに、パン派は75.6ポイントと平均を下回り、ご飯派は77.6ポイントで平均を越した。両者の間にはなんと2ポイントもの差がある。日本人は米を食うべきだというエセ保守的な結論に行きついた。某製パン会社の「朝はパン♪」というCMは残念ながら間違いである。朝はご飯である。もしかすると我が校にコイン精米所ができるのも時間の問題かもしれない。
ひいきのプロ野球球団別のセンター得点率の順位を見ていくが、ひいきの球団がないと答えた人が多く有意なデータは得られなかったため、センター得点率は掲載しない。コメントのみさせていただく。
<セ・リーグ>
1位 阪神タイガース
…セパ合わせてもぶっちぎりの1位であった。ペナントの順位とは大違いで驚きを禁じ得ない。
2位 横浜DeNAベイスターズ
…絡シーズン終盤で失速したが、ラミレス体制は国分寺高校の受験生には恩恵をもたらしたのだ。
3位 広島カープ
…センター得点率でもAクラス入り。カープファンの皆様、センター試験会場には赤ヘルで行くように。
4位 読売ジャイアンツ
…今年の巨人はセンター得点率では低調。来年に大型補強の効果がセンター得点率にも反映されるか。
4位(同率)中日ドラゴンズ
…まさかの巨人と同率。コアな中日ファンは激怒するに違いない。これ以上の言及は控える。
6位 東京ヤクルトスワローズ
…きっと怪我人が相次いだのだろう。いや、センター試験と怪我は関係があるのか。それすらわからない。
<パ・リーグ>
1位 福岡ソフトバンクホークス
…球団戦力が充実しているとセンター得点率も充実するのだろう。優勝おめでとう。
2位 北海道日本ハムファイターズ
…ソフトバンクに肉薄するも2位でゴールイン。それでも安心して日ハムファンはセンター試験は安心していい。
3位 東北楽天ゴールデンイーグルス
…楽天がAクラス入り。安定感のあるセンター得点率を今シーズンも期待したい。
4位 埼玉西武ライオンズ
…主力の海外移籍やFAが響いたか。ペナント優勝で満足し、CSに敗れ、センターも敗れる。
5位 千葉ロッテマリーンズ
…数字は申し上げらませんが惨憺たる成績。6月で優勝可能性消滅しているレベルのセンター得点率です。
6位 オリックス・バファローズ
…失礼を承知で申し上げますが編集部一同、オリックスファンがいたことに驚きを禁じえませんでした。